子どもがご飯を自分で食べることは、大切な発達段階の一つです。
自分で食べられたという満足感を得たり、手指の運動機能の発達や五感・脳を刺激します。しかし、自分で食べ始められる時期には個人差があるもの。
今回は、「いつから自分で食べ始めていいの?」「どう練習すればいい?」と悩んでいるパパママへ、子どもが自分で食べるようになる時期の目安や練習の進め方、よくある悩みへの対処法を詳しく紹介していきます。
子どもが自分で食べるのはいつから?時期と目安のサイン

子どもが自分でご飯を食べるように促していいのはいつ頃からなのか、悩みますよね。まずは子どもの月齢ごとに、食事に関する発達段階を知っておきましょう。
発達段階による目安
子どもがご飯を自分で食べられるようになるには、発達ごとに段階があります。まずはパパママが、これから紹介する発達段階の目安を頭に入れておきましょう。
手づかみ食べ(9~11ヶ月頃)

離乳食中期頃になると食べるときの姿勢が安定し、食べ物への興味も高まります。この頃から歯茎で潰せるかたさのものを、手で掴んで口に運べるようになります。
柔らかく煮たスティック状の野菜や、小さめのおにぎりなどを出してあげるとよいですね。食べ物を握ったり、こねたりする子もいますが、これも五感で感じ取っているサイン。余裕のあるときは少し見守ってあげましょう。
自分の意志で食べ物を選んだり、手指で握る動作はとても重要な経験です。
スプーン使用(12~18ヶ月頃)

手づかみ食べで、口に食べ物が上手に運べるようになった1歳頃からは、スプーンの練習を始めてみるといいでしょう。トロッとしたお粥やヨーグルトは、練習に最適。
最初はうまく料理をすくえず、口に運ぶのも難しいので、しばらくはパパママが手を添えてサポートをしてあげてください。
中には手づかみ食べを嫌がり、早くからスプーンを持ちたがる子もいるので、子どもの性格や発達段階に応じて対応してあげてくださいね。
フォーク使用(18~24ヶ月頃)

スプーンに慣れてきたら、フォークにも挑戦してみましょう。スプーンの用途とは違い、食べ物を刺して使う必要があります。
食べたいものを狙ってフォークを動かし、力を入れて食べ物を刺すのは幼児には難しいです。このときも最初は大人が手を添えて、一緒に動かしてあげてくださいね。
このときにスプーンやフォークを持つ手と反対の手で、お皿を押さえた方が上手に食べられることも教えてあげると、自然とマナーの習得にも繋がりますよ。
自分で食べる準備ができているサイン

実は子ども自身が、自分で食べる準備ができているサインを発していることがあります。
以下の4つに当てはまるものがあれば、パパママ・子ども自身の心に余裕があるタイミングで始めてみてもいいですね。
食べ物に手を伸ばす
離乳食が進んでくると、自分で食べ物を触りたがることがあるでしょう。これは徐々に手づかみ食べを進めてもいいサインです。食べ物に興味が湧き、自分で食べたいという意欲が高まっている証拠。つい「食べ物を触らないの!」と言ってしまいがちですが、せっかく芽生えた自我の芽を摘まないように気をつけましょう。
大人の食事に興味を示す
大人の食事の様子をじっとみたり、欲しがるようになることも食べ物に興味が出てきたサインです。大人がおいしそうに食べている姿は「真似してみたい」という子どもの発達や食欲にも大きく関係します。なるべく早いうちから、パパママの食事の様子を子どもに見せておくといいですね。
座位が安定する
腰が安定し、ゆらゆらせずにしっかりと椅子に座れたり、食事の間姿勢を崩さずに集中できるようになることもポイントです。体が発達し、物を握る力や咀嚼力がアップしている証拠なので、このタイミングで自分で食べる練習を始めてみるといいでしょう。
物をつかめるようになる
遊びの中でおもちゃに手を伸ばしたり、握って掴めるようになっていれば、手づかみ食べでも同様の動作ができると考えられます。掴みたいものとの距離感を適切に取ったり、手指を握ったり開いたりする動きができているかなど、食事以外の子どもの様子からも判断できます。
自分で食べる練習の進め方
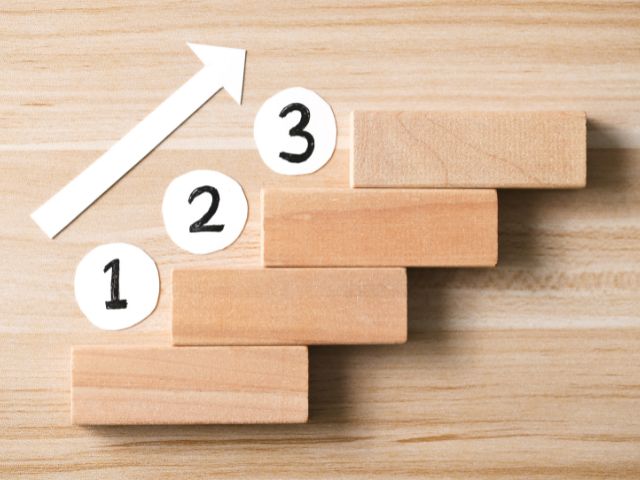
次に、自分で食べる練習を始めるときの進め方を詳しく解説します。「自分で食べる」とはいえ、料理やスプーン・フォークを渡せばよいわけではありません。子どもが自分で食べるのに適した献立や準備をしてあげましょう。
食べやすいように食事を工夫する
ついつい一口で食べられるサイズにカットしてあげたくなってしまいますが、手づかみ食べを始める際には柔らかくした食材をスティック状にカットしてあげましょう。スティック状だと握りやすく、自分で噛み切る練習になります。
また、スプーンやフォークは大人でも料理ごとに使う場面が違いますよね。子どもの献立でも、スプーンですくうメニューと、フォークで刺して食べられるメニューを考えてあげましょう。
盛り付けを工夫する
自分で食べる用のご飯やおかずは大皿ではなく、あらかじめ一人分ずつ取り分けておきましょう。
大皿からだと、好きなものばかり取って栄養バランスが偏ってしまったり、どのくらいの量を食べたかの把握が難しくなります。
子ども自身で盛り付けをするのも効果的。パパママのお手伝いをする感覚になり、一層食事に意欲的になるので、食育の観点からもよいですね。
エプロンや食器を準備する
手づかみ食べを始める前に、エプロンや子どもの発達段階に合った食器を用意しましょう。
エプロンは防水で、サッと洗い流せるタイプのものがおすすめです。
スプーン・フォークは喉奥まで入らないように短いものや、口に運びやすいように柄が曲がったものなど様々な形のタイプがあります。
また器も、落ちないようにテーブルにくっつくものや、食べ物がすくいやすいボウル型など、月齢や悩みに合わせた仕様のものが販売されていますよ。
▼幼児食の食器の選び方について詳しくはこちら
床や周りの汚れ対策をする
自分で食べるようになったばかりの子どもに、食べこぼしはつきもの。中には食べ物を投げてしまう子もいます。
食事のたびに盛大に汚れた床やテーブルの掃除をするのは本当に大変ですよね。
少しでも負担を減らすために、前もって椅子の下にシートを広げておいたり、食べ物が飛んでも大丈夫なように周りに大事なものをおかないなど、対策は万全にしておきましょう。
mogumoには子どもが自分で食べやすいメニューが勢ぞろい!

引用:mogumo公式サイト>かりっとジューシーからあげ(醤油)
自分で食べるのに適したメニューを、mogumoの商品を例に紹介します。mogumoは、幼児向けの冷凍宅配食サービスです。1歳6ヵ月以降の子ども向けのメニューが、常時24種類以上取りそろえられているのが特徴。
メニューは全て管理栄養士が監修しており、栄養バランスや塩分量もしっかり考えられているので安心です。素材や出汁の風味を大切にしており、大人が食べても満足のおいしさが魅力的。
電子レンジで簡単にできる上、どのメニューの野菜も柔らかく調理され、魚の骨はできる限り除去されているので、お腹がすいた子どもを待たせることがありません。
<mogumoサービスの概要>
| 公式サイト | mogumo |
| 対象年齢 | 1歳6ヵ月頃〜 |
| 価格 | ・8食セット:1食あたり543円 ・12食セット:1食あたり525円 ・18食セット:1食あたり478円 |
| 送料 | エリアによって異なります。詳細はこちらをご覧ください。 |
手づかみで食べやすいメニュー

おにぎりやパンは手づかみで食べやすいメニューです。自分で噛み切れる、手づかみ食べにちょうどよいサイズ感が嬉しいですよね。
鮭とわかめのまぜおにぎりは、これ一つで栄養バランスを整えやすく、常備しておきたいおすすめメニューです。
1歳6ヵ月頃になると食べ物を掴む力も調整できるようになってきて、力任せに潰してしまうことも減ってくるので、子どもがペロリ!あまいにんじんパンのような柔らかいパンもOK。
ほんのり甘いじゃがいもコロッケは、手づかみでも食べやすい大きさや柔らかさですが、スプーンやフォークでも食べられる、どの発達段階にもおすすめの商品です。
スプーンでパクパク食べれるメニュー

スプーンで食べやすいのは、柔らかい食材やとろみのついた料理です。辛くないやさしい麻婆あんかけは、ご飯にのせるとお米がまとまり、パラパラ落ちにくいので食べやすくなります。ほうれん草とコーンチキンのホワイトシチューも、すくいやすいとろみがスプーン食べに適しています。柔らかく調理された野菜がたくさん入っているので、野菜不足が心配な幼児期の食事にぴったりです。
まろやかな旨味のトマトとナスのミートソースは、ご飯やショートパスタ(マカロニやペンネ)にかけるのがおすすめ。まだ長いパスタを食べるのが難しい子でも、食べやすくなりますよ。
フォークの練習にぴったりメニュー

フォークを使用する際のメニューは、刺しても形が崩れにくい適度な柔らかさのものや、麺類などひっかけやすいものにしましょう。
ダシ香るもちもち五島うどんは柔らかいのにもちもちで、子どもに大人気のメニュー。お好みでわかめやねぎ、揚げ玉などをかけると満足感が増します。
ふっくら切り身のサバの味噌煮は、食べる際にパパママが一口サイズに崩してあげると、フォークでも食べやすくなりますね。
かりっとジューシーからあげ(醤油)は、中から肉汁が溢れるほど柔らかく、フォークで刺す練習・自分で噛みちぎる練習に適した商品です。
自分で食べる!スプーン・フォークの練習方法

スプーンとフォークを練習する際の、具体的な方法を紹介します。簡単に思えるスプーンやフォークも、子どもにとっては持ち方・すくい方・口への運び方など初めての動作の連続です。根気よく、丁寧に教えてあげましょう。
持ち方の教え方
まずはスプーンを上から掴む「上手持ち」から始めましょう。力を入れて握ることができ、口に入れるときに手首を返す必要もないので、子どもにとっては掴みやすい持ち方です。
個人差はありますが、2歳頃になったら少しずつ「下手持ち」に移行し、3歳頃には大人と同じ「鉛筆持ち」を練習させてあげると無理なく上達をサポートできます。
練習に適した食材
スプーンには、とろみのある汁物やヨーグルトなどが食べやすいです。すくいやすく、こぼれ落ちにくいので、子どものストレスも少なく済みます。
フォークの練習には、適度なかたさ・大きさの食材がよいでしょう。フォークで刺したときにボロボロと崩れてしまったり、小さすぎたり大きすぎて持ち上げられない大きさだと食べづらいです。スプーンやフォークで食べやすい形状や柔らかさに調整してあげてくださいね。
使いやすい食器の特徴
スプーンの練習を始めたばかりの子どもにとって、平皿などの浅い器は、食べ物がすくいにくく、こぼしてしまいがちです。
器の縁に沿ってすくえると食べやすいので、なるべく縁が深めのものや内側にカーブしているものを選んであげましょう。
何度も失敗してしまうと、せっかく挑戦したスプーンやフォークが嫌になってしまうこともあるので、細かな配慮をしてあげましょう。
声掛けをしてサポート
自分で食べる意欲が芽生えた子どもは、パパママから応援されたり、褒められることが大きな自信に繋がります。
できないことを指摘するのではなく、「こぼさないでお口に運べたね」「昨日より上手にフォークが持てたね」など、できたことや成長していることをどんどん口に出してあげてください。
アドバイスをするときも「こうするともっとおいしく食べられるよ!」と子どもが改善したくなる声掛けをこころがけましょう。
「自分で食べる」をサポートする環境づくりのポイント
.jpg)
子どもが自分で上手にご飯を食べられるように、環境の面でもサポートしてあげましょう。先輩ママたちが使って便利だったグッズや選び方を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
子ども用の食器選ぶ
手づかみ食べには平皿がよいですが、とろみのある料理や汁物は、深さのある食器を使いましょう。器をひっくり返されてしまう心配がある場合は、吸盤や滑り止めがついた皿がおすすめです。
洗いやすさや、レンジ調理が可能かなどの機能性も大事なポイントですね。スプーンやフォークは怪我防止のために先端に丸みのあるものを選びましょう。持ち手が太めで握りやすく、落としても壊れにくい木製やプラスチック製のものが安心です。
椅子とテーブルの高さ
食事中の姿勢にも気をつけましょう。姿勢が悪いと食べこぼしや、集中力の欠如にも繋がります。
椅子とテーブルのちょうどよい高さの目安は、椅子に座ってテーブルに肘をついたときに肘の角度が90度になっている状態。
また、足はしっかりと床や足置きにつくようにしてください。ブラブラと宙に浮いた状態は避けましょう。足の裏が床や足置きについていると踏ん張りが効くので、体に力が入りやすくなり咀嚼力がアップします。
床マット・エプロンを活用
食べこぼしは一般的に、安定して食事ができる4歳頃まで続くと言われています。食事のたびに掃除をするのは、大変ですよね。
負担を減らしたいときは、事前にテーブル下に床マットやシートを敷いておくと、サッと拭き取るだけで掃除が完了。洗いやすく、繰り返し使えるビニールやシリコン性のエプロンも用意しておきましょう。
大人が口うるさく注意することが減ると、子どもも思いのまま食べられるので、汚れ防止グッズは必須ですね!
食事時の雰囲気作り
1番大事なことは、食事が楽しいものだと子どもにわかってもらうことです。
そこでまず、パパママは「おいしいね」「ママも〇〇君と同じおかず食べてみようかな」と、穏やかな雰囲気で食事を楽しんでください。
笑顔でおいしそうにパクパク食べている大人の姿をみて、食事に興味をもち、「一緒に食べたい」「真似をしたい」と意欲が湧きます。
できないからと焦らない
最初から上手に食べられないのは当たり前です。頑張って工夫してみたけれど自分で食べることが難しく、子どももパパママも疲れてしまうようであれば、無理せず一旦お休みするのも一つの手です。
もう一度仕切り直して、子どもが自分で食べたがるまで待ってあげましょう。時期が来れば、食事への興味が持てたサインが出てくるので、タイミングを見計らってあげましょう。
自分で食べるのはいつから?よくある悩みと対処法

ここからは子どもが自分で食べることへのよくある悩みや心配、対処法を解説します。同じ悩みをもっているパパママもたくさんいるので、焦らずに子どもの様子を観察することから始めてみましょう。
自分で食べられないのは発達の遅れ?
手づかみ食べやスプーンなどを使ってうまく食べられないからといって、発達に問題があるとは限りません。まずは自分で食べられない理由を探してみましょう。
- 手指の運動機能が未発達
- 食事への興味がない
- 食欲はあるが集中力が続かない
- 偏食/好き嫌いが多い
うまく食べ物が掴めていない場合は、毎日練習することで上達するので、根気よく取り組みましょう。
その他の理由で、試行錯誤しても改善しないときは無理強いせず、時期を改めてみてもいいですね。どうしても気になるときは、地域の子育て相談窓口や医療機関で相談してみましょう。
遊び食べが多くて進まない…
出されたご飯や食器で遊んでしまう「遊び食べ」。これは幼児期の成長過程の一つです。特に手で食べ物をこねたり、食器同士をぶつけて音を出したりするのは、食材や食器に興味を持っている証拠なので、いい経験になります。
ただし、料理を床に投げ捨てたり、食べる意欲がないと感じるときは食事を切り上げてしまうのも手です。
このときに無言で下げたり、叱ってしまったりするのではなく、「あと一口頑張れるかな?」「ご飯はまた後でにしようね」と、食事への意欲をそがないようにしましょう。
自分で食べたがらない場合はどうすればよい?
前述した「自分で食べる準備ができているサイン」が出ているかもう一度よく観てみましょう。もしまだ早いようなら時期を改めてもよいでしょう。
「手づかみなら食べられるけれど、スプーンは持ちにくいから食べたくない」という子や、逆に「手が汚れるのが嫌で手づかみ食べを拒み、スプーンなら食べられる」という子もいます。
体調や気分にもよるので、叱ったり無理強いせず、ゆったり見守り、サポートしてあげてください。
食べこぼしが多くて気になる…
食べこぼしが多くて気になる場合は、以下の点を再度確認しましょう。
- 椅子やテーブルの高さが合っているか
- 食器が月齢に合ったものか
- 食事に集中できる環境か
- 食事の形状が適切か
上記のように食べにくさや集中力の欠如が原因の場合は、調理法や環境設定を見直すことで対処できます。
まれに子どもの口腔や運動機能に問題がある場合もあるので、心配なときは医療機関で診てもらいましょう。
子どもが自分で食べられるようサポートしよう!
今回は、子どもが自分でご飯を食べるための環境設定・食事中のサポートについて紹介しました。
紹介している発達段階や月齢は、あくまで目安です。他の子と比べて焦ってしまわないよう穏やかに見守ってあげてくださいね。大事なことは、繰り返し根気よく、丁寧に進めることです。
もしうまく進められないと悩んだときは、地域の子育て支援の窓口や医療機関に相談し、みんなで子どもの発達をサポートしていってくださいね。
食事の準備に迷った際は、mogumoの商品を活用してみてください。献立を考えたり買い物する手間や、調理時間を大幅にカットでき、安心安全に子どもの健康に配慮したおいしい料理が手軽に準備できますよ!
→【初回半額】子どもが喜ぶメニューが豊富!mogumoの幼児食宅配サービス
※キャンペーンは時期により内容が変わっていることがありますのでご注意ください
参考文献:堤ちはる・土井正子(編著)子育て・子育ちを支援する子どもの食と栄養|萌文書林
[PR] 子どものごはん準備に悩むママへ
仕事おわりに保育園へお迎えに行って、
帰りにスーパーで夜ご飯のお買い物。
正直言って、「毎日しんどすぎる..!」
そんなママの味方が冷凍幼児食のモグモ。
コスパの良い幼児食宅配を利用したいママはチェックしてみてください。
 について詳しく見る
について詳しく見る















